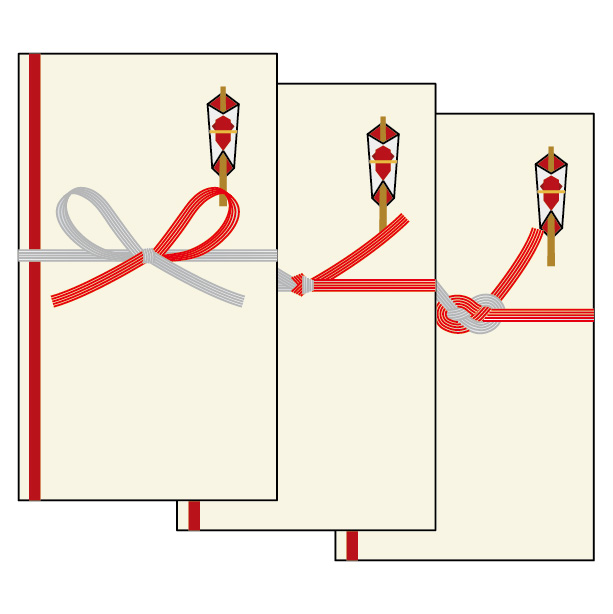文章には、
じっくり伝えたいものもあれば
端的にインパクトを残したいものも
あります。
書き手は、読み手に対しどのように
伝えたいのか、によってその書き方が
変わってきます。
今回は、読み手に
文章を読み進めてもらうための
文章の書き方を紹介します。
「結果」を先に伝える文章構成
1)概要、要約(Summary)
2)詳細(Details)
3)まとめ(Summary)
この文章構成は、
新商品や研究の発表会をはじめ
各種セミナー説明など
テーマには興味があるが、
詳しい内容までは知らない場合に適しており
「SDS法」と呼ばれています。
この方法は、
伝える内容の利点をまとめた要点から入るため、
読み手が聞く体制になりやすく
その先の内容を理解しようとする働きを
促すことができます。
例えば
<概要>
この△△というドリンクは、1日1回
コップ一杯飲むだけで、整腸と
ダイエット効果が期待できる
健康サポート商品です。
<詳細>
便秘や肥満気味の方は、まずは腸内を
きれいにし、働きやすくする必要があります。
このドリンクには、食物繊維が○%含まれ
ビタミン、ミネラル・・・・・など
腸内環境を改善する豊富な栄養素を
○種類もバランス良く配合しています。
<まとめ>
△△は、あなたの腸の働きを改善し
健康とともに脂肪の燃焼に効果を発揮してくれます。
いかがでしょう。
要点が絞られているので
読みやすく、理解しやすい内容に
まとまっていますよね。
このように、文章の作成には
いくつかの技法があります。
みなさんも、使い分けてみてくださいね。
<あわせて読みたい関連記事>
話しを簡潔に、分かりやすく伝える方法 はコチラ
起承転結は、使わない はコチラ