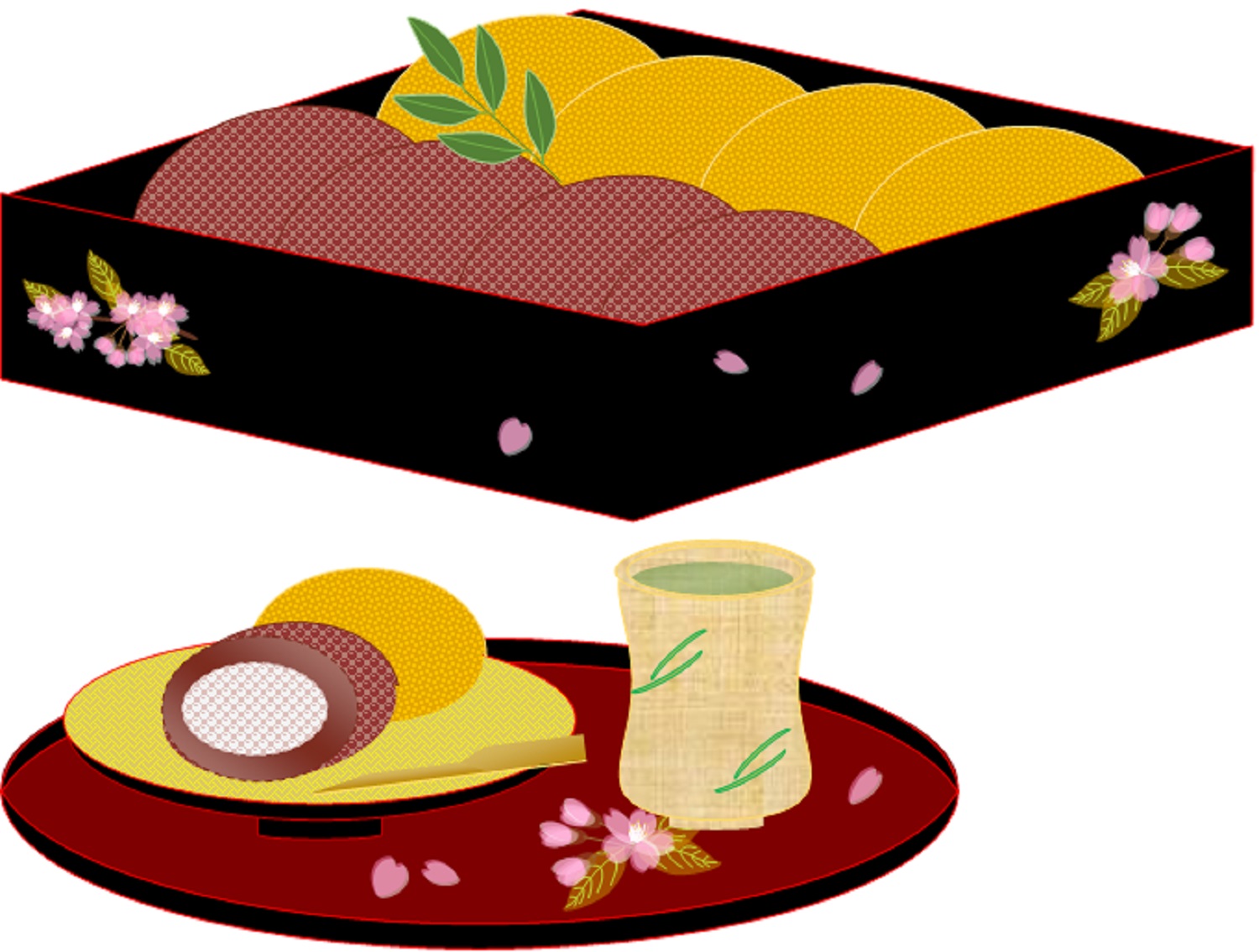「弱冠30歳の彼が手掛けた
このプロジェクトの成功は、
火を見るより明らかだ」
サクセスストーリーとして
ありがちな文章ですが。。。残念 (>_<)
「弱冠」とは、
もともとは、20歳の男性のことを指す言葉で
古代中国で男子の20歳を
「弱」と呼んだことに由来します。
このことから、
30歳を弱冠というのは、
語弊があることになります。
ですが、現在では20代やそれ以下の男性、
または女性も指すようになるなど、
言葉の守備範囲が広がりつつあります。
「火を見るより明らか」とは
疑いの余地がないこと、
明白なさまを言います。
成功について、火を見るより明らか
という表現は、一見すると
正しいように思いますが。。。
「火を見るより明らか」は、
「失敗は、火を見るより明らかだ」のように
悪い結果や悲劇的なときに用いるのが
正しい使い方なのです。
よくよく考えてみてください。
成功について
「疑う余地がない」と言っている時点で
「成功を疑っていた」ということになり
失礼な言い方になるのです。
みなさんは、ちゃんと使えていますか。